超大ヒット・シリーズの第3弾『キングスマン:ファースト・エージェント』が絶賛公開中だ。本作は、『キングスマン』(2014)、『キングスマン:ゴールデン・サークル』(2017)の前日譚。第一次世界大戦前夜の時代を舞台に、イギリスの諜報機関「キングスマン」の誕生秘話が描かれる。前2作に引き続きマシュー・ヴォーンが監督を務めるほか、レイフ・ファインズ、ジェマ・アータートン、リス・エヴァンス、マシュー・グッドといった豪華キャストが出演。

だがこの最新作は、スパイ映画というよりもストレートな反戦映画として作られている。その理由は何なのか?という訳で今回は、話題作『キングスマン:ファースト・エージェント』をネタバレ解説していきましょう。
映画『キングスマン:ファースト・エージェント』あらすじ
時は1914年。イギリスの名門貴族であるオーランド・オックスフォード公爵は、世界大戦を裏で操る謎の組織の存在を突き止める。彼らはロシア、ドイツ、イギリスにスパイを送り込み、世界をさらなる混乱に陥れようとしていた。オーランドたちは戦争を止めるために奔走する……。

※以下、『キングスマン:ファースト・エージェント』のネタバレを含みます。
パブの酔っ払いトークから生まれた『キングスマン』
表向きは高級紳士服テーラーだが、その正体は世界最強のスパイ組織。そんなキングスマンのアイディアは、監督のマシュー・ヴォーンとコミック・ライターのマーク・ミラーがパブで酔っ払っている時に生まれた(二人は『キック・アス』(2010)で、映画監督と原作ライターと言う形でタッグを組んだ仲だ)。
「マークとパブで酔っ払っていたのが始まりだった。(中略)スパイ映画がいかにシリアスになっているかということに文句を言っていたんだよ。楽しい映画を作ろうじゃないか、とね。さっそくマークが書いてきて、僕は読んでみた。僕はそれを一読して、これは本当にやるべきだ、と思ったんだ。そして、彼はそのコミックを完成させたんだよ」
(マシュー・ヴォーンへのインタビューより抜粋)
https://www.ign.com/articles/2014/11/20/matthew-vaughn-talks-choosing-kingsman-the-secret-service-over-x-men-days-of-future-past-changing-the-comic-and-bringing-fun-back-to-spy-movies
そのコミックこそが、『キングスマン』の原作となった『The Secret Service』。マシュー・ヴォーンはすぐさまこの映画化に取り掛かろうとしたが、当時彼は『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』(2011)を仕上げたばかりで、その続編となる『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)の製作も控えていた。
脚本が届いたタイミングが同時だったために、彼はどちらか一方の作品を選ぶ必要があった。ドル箱シリーズの続編を選ぶべきか、海のものとも山のものともつかない未知の作品を選ぶべきか。悩んだ末にマシュー・ヴォーンは、本人曰く「おそらく人生で最もクレイジーな決断」をして、『キングスマン』の製作に取り掛かる。
理屈抜きでとにかく楽しいスパイ映画を。そんな想いで作られた『キングスマン』は、世界興収4億ドルを超える大ヒット。続く『キングスマン:ゴールデン・サークル』も、同じく世界興収4億ドル超えを果たした。

だがシリーズ第3弾となる『キングスマン:ファースト・エージェント』は、明らかにこれまでとはテイストが異なる。毒っ気のあるユーモア、過剰なまでに誇張されたアクションを抑制し、非常にシリアスなトーンで描かれているのだ。その理由は、第一次世界大戦というヨーロッパ最大の悲劇を、真正面から捉えているからだろう。
『王になろうとした男』から着想を得た、キングスマン誕生譚
筆者がこの映画を観て驚いたのは、20世紀初頭の第一次世界大戦前夜の歴史を、きっちりと描いていること。それをキングスマン誕生という虚構の歴史と組み合わせることで、まるでクエンティン・タランティーノの『イングロリアス・バスターズ』(2009)のような(こっちは第二次世界大戦でしたが)、ヨーロッパ偽史という作りになっているのだ。
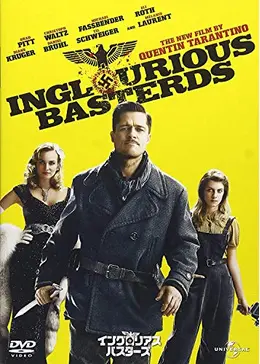
このアイディアは、マシュー・ヴォーンがジョン・ヒューストン監督の『王になろうとした男』(1975)を観直したことから生まれた。カーネハン(マイケル・ケイン)という老退役軍人が、新聞記者に「カーフィリスターンの地で王になる」というかつての夢を語って聞かせる。そして物語は過去に戻り、カーネハンとドレイボット(ショーン・コネリー)の二人が、いかにその夢を掴もうとしたのかが綴られていく…。
ここでマシュー・ヴォーンに天啓が閃く。『王になろうとした男』のように、「王(キングスマン)になる男」のドラマが描けるのではないか?と。
「時代劇のような壮大な戦争ドラマで、『キングスマンになる男』と言えば、ハリウッドのみんなが “おお、エキサイティング! “と言ってくれるんじゃないか、という妄想に取り付かれたんだ。(中略)映画を見て書き始めた……創造性というのは、説明するのが難しいんだよね。なぜこれをしたのか?やりたかったというのは別として。ただ、やりたかったんだ」
(マシュー・ヴォーンへのインタビューより抜粋)
https://screenrant.com/kings-man-movie-matthew-vaughn-interview/
ひょんなことから、キングスマン誕生譚の着想を得たマシュー・ヴォーン。歴史大作を作ることは、彼の念願でもあった。
「僕が目指したのは、大掛かりで、壮大なアドペンチャー作品だ。子供の頃、『アラビアのロレンス』のような映画がたくさん上映されていて、いわゆる叙事詩だが全く退屈することはなかった。ちょうど、あのジャンルをまた盛り上げたいと考えていたんだ」
(プロダクション・ノート マシュー・ヴォーンへのインタビューより抜粋)
本作は、主人公オーランド・オックスフォード公爵が、息子のコンラッドと妻のエミリーと共に捕虜収容キャンプを訪問する場面から始まる。オーランド暗殺を狙った狙撃手によってエミリーの命が奪われ、国家のために兵士に志願したコンラッドも戦争で失うことに。最愛の妻と息子を失った哀しみから、オーランドは独立機関としてのスパイ組織「キングスマン」を立ち上げるのだ。

さまざまな悲劇に彩られた本作が、これまでの『キングスマン』シリーズと同じような毒っ気ユーモア・テイストで描けるハズがない。『キングスマン:ファースト・エージェント』は、『キングスマン』という大ヒット・シリーズのエピソード・ゼロ的な体裁を取りつつも、その中身は戦争の恐ろしさと無意味さを実直に描いた、堂々たる反戦映画なのだ。
オーランドは平和主義者としてのポリシーをかなぐり捨てて、シェパードに宣戦布告することを決意する。もちろんそれ自体は暴力の肯定かもしれないが、オーランドはこれ以上戦争の犠牲者を出したくないという想いから、戦いを挑むのだ。繰り返すが、この作品は諜報活動によって第一次世界大戦を終わらせようとする、れっきとした反戦映画なのである。
ドイツがアメリカに介入した証拠を手に入れようと、最前線でコンラッドが奮闘する姿はもうほとんど『1917 命をかけた伝令』(2019)。筆者は途中から、「今俺が観ている映画は『キングスマン』の最新作だよな?」と自問自答しながら観ておりました。これもエピソード・ゼロだからこそ出来る芸当だろう。
思えば、マシュー・ヴォーンが唯一監督として参加したX-MENシリーズの『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』も、どのようにX-MENが生まれたのかを描く誕生譚だった。彼はエピソード・ゼロものがいたくお好きらしい。
一人三役に込められた強烈なブラック・ユーモア感覚

本作には、“羊飼い”と呼ばれる男を中心とした謎の組織シェパードが登場。“羊飼い”は、スコットランドを無理やり併合したイングランドに恨みを抱いていて、第一次世界大戦を勃発させて窮地に陥れようと画策する。スコットランド人の彼は、イギリスという超大国の滅亡を狙っているのだ。
ご存知のように、イギリス(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)はイングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4つの地域から成っている連合国。スコットランドは、1707年にイングランドと合併するまでは独立した国家だった。アイデンティティの違いから19世紀末ごろより独立運動が盛んとなり、その歴史的背景が今作に活かされている。おそらくマシュー・ヴォーンは、彼らを絶対悪ではなく、歴史の犠牲者として描いているのではないか。少なからず、イギリス人である彼のフラットな視座がこの作品に込められているような気がしてならない。
それにしても、第一次世界大戦の引き金となったサラエボ事件も、「実はシェパードの仕業でした」という嘘歴史として堂々と語ってしまうストーリーの強度ったら!しかもこの秘密結社のメンバーは、占星術師やスパイなど歴史上の人物によって構成されているのだ。
グリゴリー・ラスプーチン(リス・エヴァンス)
帝政ロシア末期に、皇帝ニコライ2世の知己を得て絶大なる権力を誇ったとされる怪僧。予知能力があったとか、いっさい手を触れずに物を持ち上げたとか、青酸カリを飲んでも2時間以上生きていたとか、とてつもない性豪だったとか、彼に関する逸話は数知れず。映画ではチャイコフスキーが作曲した「序曲 1812年」に乗せて、バレエダンサーのような攻撃を繰り広げた末に、ポリー(ジェマ・アータートン)の銃弾によって倒れるが、実際にはユスポフ一派によって暗殺されている。『ノッティングヒルの恋人』(1999)のおかしな同居人や、『アメイジング・スパイダーマン』のカート・コナーズ博士など、変わり者ばかり演じているリス・エヴァンスがラスプーチン役というのがナイスなキャスティング!
マタ・ハリ(ヴァレリー・パチナー)
パリを中心に活躍した有名ダンサーにして、その正体はフランス軍およびドイツ軍のスパイ。映画ではウィルソン大統領(イアン・ケリー)にハニー・トラップを仕掛けて、アメリカが参戦しないように仕向ける。実際には第一次世界大戦中にスパイ容疑で捕らえられ、有罪判決を受けて処刑された。その際に彼女は目隠しを断り、発砲直前に兵士たちに投げキッスをしたと伝えられている。
エリック・ヤン・ハヌッセン(ダニエル・ブリュール)
ヒトラーお気に入りの預言者だったとされる、手品師・占星術師。ドイツ国会議事堂放火事件を予言したことで注目を集め、社交界にも人脈があった。ナチス政権が樹立された暁には「オカルト省」を設立して、その初代大臣に就任する予定だったと言われている。1933年にナチス突撃隊によって暗殺されたが、その理由は未だに謎。ヒトラーと彼の関係を妬んだ何者かによる謀略、との説もある。
ウラジーミル・レーニン(アウグスト・ディール)
言わずと知れたソ連建国の父。1917年に十月革命を成功させてロシア・ソビエト連邦社会主義共和国を樹立、その最高指導者として絶大なる権力を誇った。まさかレーニンまでがシェパードの一員とは! このトンデモ発想こそが、マシュー・ヴォーンの魅力なり。
だがこの映画で最も大胆なのは、イギリス国王のジョージ5世、ロシア皇帝のニコライ2世、ドイツ皇帝のヴィルヘルム2世の3役を、トム・ホランダー一人に演じさせていることだろう。彼らはいとこ同士で外見がよく似ていた、ということから生まれたアイディア。マシュー・ヴォーンはさまざまな文献を読み漁り、「お互いの服を交換して国王と皇帝が入れ替わったが、誰も気づかなかった」というエピソードも見つけたという。いとこ同士である彼らがヨーロッパを支配していたという、おかしさと恐ろしさ。
『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』(1964)で、ピーター・セラーズがストレンジラヴ博士、マンドレイク大佐、マフリー大統領、タージドソン将軍の4役を演じていたのと同趣の、強烈なブラック・ユーモア感覚があるのだ。
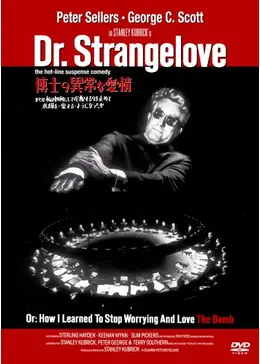
演じたトム・ホランダー自身のコメントを見てみよう。
「マシュー・ヴォーンの名案だよ。よく知られているように、ヨーロッパの王族というのは皆、親戚関係にある。だからこそ、戦争になるんだ。同盟したり、ライバル意識を燃やしたりするからね。彼ら3 人はいとこ同士だったので、同じ俳優が演じるのは気の利いたジョークだ。ジョージとニコラスの二人は、とてもよく似ていた。違って見えるのはドイツ皇帝だ。そしてドイツ皇帝は、この映画では、その二人をいじめる兄のような存在なんだ」
(プロダクション・ノート トム・ホランダーへのインタビューより抜粋)
『キングスマン』創造者たるマシュー・ヴォーンだからこそできた反戦映画

(ラスプーチンとの格闘シーンは除いて)極めてシリアスな反戦映画として進行する、『キングスマン:ファースト・エージェント』。残り30分くらいになってから急激にスイッチが入り、毒っ気のあるユーモア、過剰なまでに誇張されたアクションのつるべ打ち状態に。やっと我々が見慣れてきた『キングスマン』モードに突入する。
この作品を鑑賞した皆さんのレビューを読むと賛否が入り乱れているようだが、さもありなん。戦争映画からユーモア満載のスパイ・アクションに変貌するという、非常に特異な作りなのだから。だがこの挑戦的な構成は、『キングスマン』の創造者たるマシュー・ヴォーンだからこそできる所業だろう。
むしろ筆者は、「ストレートな反戦映画を作っても、きっと客は来ない。だったら『キングスマン』外伝という形でメッセージを伝えられないか?」とマシュー・ヴォーンが考えたのではないか、と想像している。『キングスマン:ファースト・エージェント』は、彼の真摯な想いが詰まった一作なのだ。
(C)2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.
※2021年12月29日時点の情報です。



